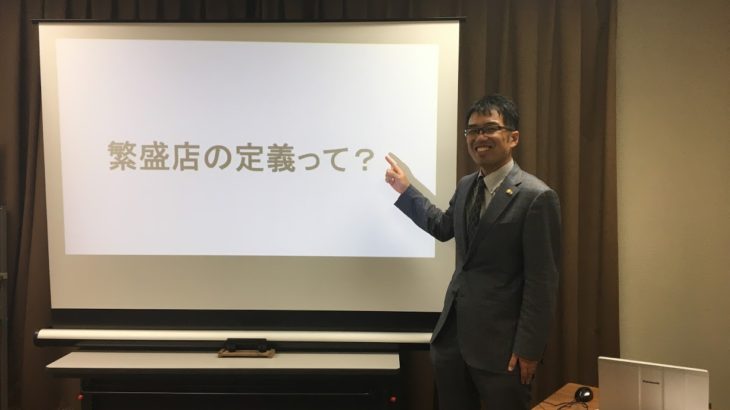【第1回 公的機関の業務を受けてこそ診断士】

2014年に診断士試験に合格,1年後に独立された安藤準さん。民間企業向けの業務も増えているという安藤さんですが,公的機関の業務は外せないと言います。その意図とは?
公的機関の業務を受けるからこそ国家資格「中小企業診断士」である
――現在,コンサルティング業務と研修講師のお仕事で大変お忙しくされていると聞いています。民間企業からの業務も増えてきている中で,公的機関から中小企業に派遣されコンサルティングする「専門家派遣」の業務も大切にされているそうですね。
専門家派遣の業務はできれば年間30社以上は訪問したいと思っています。
私が専門家派遣の業務を継続的に行っているのには,二つの理由があります。
一つは,さまざまな会社をサポートすることにより,診断士として支援内容の引き出しが増えていくためです。民間企業と顧問契約を直接結んだ場合,1社のことを深く知られるという魅力がある一方で,相談内容も偏りがちです。診断士は,経営の町医者で,どんな相談にも対応できなければなりません。そのような意味でも,専門家派遣の業務を通じて,多様な業界,様々な規模の企業の相談に乗ることは能力向上につながります。
もう一つは,「診断士だから」です。先輩診断士が「公的機関の仕事をするからこそ,国家資格の診断士なんだ。民間の仕事だけしたいなら,診断士資格をとる必要はない」をおっしゃっていました。その通りだと改めて思いました。診断士として名乗る以上は,公的な業務を通じて中小企業を支援することは使命であると考えています。
全力を出し切って支援するのが専門家派遣
――専門家派遣ではどのようなことに気を付けているのでしょうか。
専門家派遣で企業の相談に乗るときには,短期間ではありますが,ひとつひとつ丁寧に対応することを心がけています。たとえ1日・1回の支援であっても,なるべく報告書や打ち合わせ資料などをアウトプットで残すようにしています。中途半端な支援を行ったり,ノウハウを出し惜しみするようなことになっては支援を受ける企業も不幸ですよね。派遣元である支援機関にも迷惑をかけてしまいます。
その場で全力を出し切って支援するのが専門家派遣だと考えています。

赤田 彩乃取材の匠メンバー,中小企業診断士
大学卒業後,人材紹介業に従事。その後,地方自治体向けコンサルティング会社にて,防災,民間活力活用等に関する調査,計画策定,制度導入支援等を実施。現在は独立し,マーケティングリサーチ,補助金や営業資料等資料作成のサポート等を行っている。研修講師として,「時短のためのずるいデザイン講座(ドキュメント作成編・チラシ作成編)」を提供し,効率的かつデザイン性の高い資料作成のノウハウを伝え,好評を得ている。