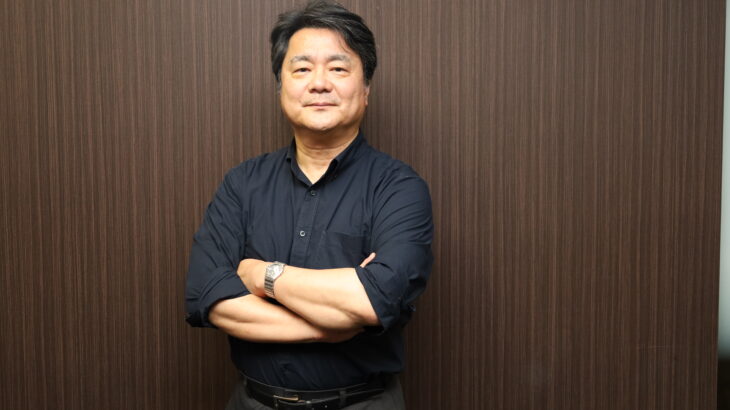【第1回 視野を広げたい】

バイオテクノロジーの修士号を持つG.Mさんは、2000年に製薬会社に入社し、以来研究職として活躍されている。中小企業診断士試験は、2021年に1次試験に合格、2次試験は2022年の2回目の受験で見事合格。本稿では医薬品開発からMBAの取得、米国ベンチャー企業との新規事業立ち上げの苦労をうかがった。
ハイリスク・ハイリターンの医薬品開発事業
G.Mさんは、理学部でバイオテクノロジーの修士号を取得し、2000年に研究職として製薬会社に就職した。
医薬品の研究開発事業は、10年以上かかることもあるうえ、ようやく臨床試験に入ってからも成功確率は約10%と低く、承認されなければ、何年もの仕事が結局1円も稼げずに終わることになる。逆に成功すれば莫大な収入があるというハイリスク・ハイリターンの事業である。その中で成功すると本当にうれしいとG.Mさんは言う。
仕事とプライベート
G.Mさんは、様々な疾患の医薬品開発に携わってきたが、最近はチームリーダーとして数名の部下を指導する立場となった。このため自ら実験することはなくなり、プレイングマネージャーとしての役割が増えている。
G.Mさんは、仕事を離れるとテニス、ゴルフ、ドライブ、旅行と多彩な趣味を持つ家庭人でもある。ゴールデンウィークは家族でウナギを食べに行ったそうである。
MBA取得を決意
医薬品の開発は高い専門性と奥深さがあるが、同時に狭い世界でもある。大学院卒業後24年間この世界に身を置いてきたが、40代後半、子供も大きくなり時間的余裕もできたこともあり、キャリアプランを見直す必要性を感じるようになってきた。そんな中、もともと財務面の勉強をしたかったこと、一般的知識を得て視野を広げたいという思いから、MBA取得を決意する。
G.Mさんは、2019年某経営大学院に入学、2年間土日中心に通学しMBAを取得した。
新規事業提案コンクールで優勝し、米国ベンチャー企業と協業プロジェクト開始
MBA取得後の2022年から、G.Mさんは米国ベンチャー企業と協業してがん患者支援に関する新規事業立ち上げに取り組むことになった。これはグループ会社の新規事業提案コンテストに応募し、200件近い応募の中、4次選考まで勝ち抜き見事優勝したことによるもの。
最初は気軽に応募したと言うG.Mさんだが、選考を重ねる中でMBAで学んだ知識を活かし、提案内容をブラッシュアップすることで優勝に漕ぎつけた。
米国ベンチャー企業との交渉を1人で対応
この新規事業では、協業先のベンチャー側には数名の担当者がついていたのに対し、G.Mさん側は経理、財務、事業計画の作成、双方の利害の調整・交渉まで、すべて1人で対応しなければならなかった。協業とは言え双方の収益配分をめぐって駆け引きがあり、その話し合いには多くの時間と労力が必要だったそうである。
協業先が経営破綻
苦労して交渉を進め、いよいよ事業開始に向け投資を始めようとした矢先、なんと先方が経営破綻してしまう。2023年3月10日、米国シリコンバレーバンクが破綻し、その影響で相手のベンチャー企業も倒産してしまったのである。先方の企業ドメインのメールはすでに機能しておらず、個人のメールに連絡しその状況は理解したものの、交渉は打ち切りとなってしまった。投資決定前だったので、幸い会社に金銭的損失はなかったが、残念な結果となってしまった。
ただ、G.Mさんは、こうした経験は深いけれども狭い医薬品開発の仕事の枠を広げ、中小企業診断士として事業を一段高い位置から俯瞰するよい機会になったと考えている。
次回はG.Mさんが多忙な業務の中、いかにして診断士試験に取り組んだかを報告する。

齋藤徹也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
半導体用フォトマスク、半導体用インターポーザ―、プリント基板、各種エッチング部品などの生産現場で、QCサークル活動、5S活動をはじめ、管理面では品質管理、生産管理、中期計画の作成などを経験。自社の10数工場で歩留まり改善、リードタイム短縮を指導した。退職後、2024年中小企業診断士登録。製造業の支援を中心に活動を模索中。東京都中小企業診断士協会三多摩支部所属。