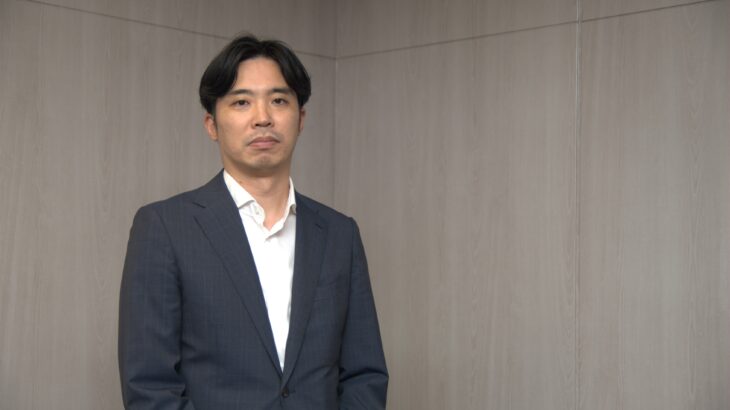【第1回 会社全体を見渡すスタートラインに】

今回インタビューした井上さんは、情報通信会社に勤める企業内診断士です。3年半におよぶ試験期間を経て2023年に中小企業診断士として登録されました。第1回は井上さんのお仕事や中小企業診断士を目指したきっかけ、受験期間に迫ります。
財務だけでなく経営全体の知識を
――現在のお仕事についてどんな業務を行っているか教えてください。
今住んでいるところは愛媛県の松山市です。高校まで住んでおり、大学は4年間大阪に行き、Uターンで地元の情報通信会社に入社して17年間の内14年間は経理業務を担当しました。日々の経理業務や会計監査の対応、付随した決算業務、数字面での分析などを行ってきました。部署としては総務部に所属しており、その中で経理、人材、採用、総務系の取締役会や株主総会など全体の雑務を行っています。
――診断士試験受験のきっかけを教えてください。
中小企業診断士は一般的に言われているように、経営全般の知識を入れることができる資格です。私自身14年間経理業務を行っているため、財務の知識はありますが、数字を扱うにしてももっと会社全体のことを知っておくべき、そのベースとなる知識を得ておくべきという思いがありました。中小企業診断士は会社全体を見渡す知識レベルの向上という意味では素晴らしい資格だと思い受験を決意しました。
――中小企業診断士を取得して業務に生きていることや業務の変化があれば教えてください。
私は主に経理業務に従事しておりますが、総務部の中でも人事面、採用、組織の能力開発をどうしたらよいかなど、人に関わる仕事も担っているため、診断士試験の事例Ⅰや企業経営理論などは財務では無い部分で会社の人事施策などで活用できているかなと思います。
――では実際に得た知識を会社でアウトプットできているということですね。
そうですね。これからですけどね。やれているというよりはやるスタートラインに立ったという感じですかね。
診断士試験は仕事との折り合い
――いつから勉強していつ合格したか教えてください。
1次試験は2018年3月頃から勉強を開始しました。その年は企業経営理論、経営情報システムの2科目を受け、経営情報システムのみ科目合格しました。翌年2019年度に残り6科目を受験し370点のギリギリで合格しました。2019年度の1回目の2次試験は不合格となり、翌年2020年はコロナで受験をスキップできる制度があったため、受験をスキップして2021年に2次試験を受験し合格しました。勉強期間は3年半程度ですかね。
――総勉強時間を教えてください。
1次試験が約500時間で、2次試験が約1,200時間。合計1,700時間程度ですね。
――2次試験1,200時間ですか、すごいですね。
受験をスキップしたため2次試験の勉強期間は2年半ありましたからね。通算すると勉強時間が長かったです。2次試験最終年に限っては約700時間勉強しました。
――それだけの時間の捻出は大変だったのでは?
まさにこの勉強期間中の永遠のテーマでした。弊社の経理業務は1月から次年度の予算があり、決算業務が閉まるのが5月中旬。そのため4ヶ月半が繁忙期となり非常に忙しい時期に入ります。そのためその期間は週末に少しやるくらいでした。幸いなことに、仕事が多忙なその期間は1次も2次も試験が無いため良かったです。繁忙期以降は集中して勉強を行いました。平日は1〜2時間、土日は制限無くやる時は10時間ほど行い、休日に重きを置いた勉強の配分でした。
――仕事とうまく両立というか折り合いをつけて行ったということですね。
そうですね。折り合いですね。両立できたとは言えないですね。

佐藤 克哉 取材の匠メンバー、中小企業診断士
1993年生まれ。岡山県出身。大学卒業後、金融機関に入社し主に法人営業に従事。経営者相手に営業を行う中で経営の知識を網羅的に学ぶため中小企業診断士を目指し2021年度中小企業診断士試験に合格。2023年4月に中小企業診断士登録。現在はファイナンス関連のコンサルティング業務に従事し、企業内診断士として活動中。