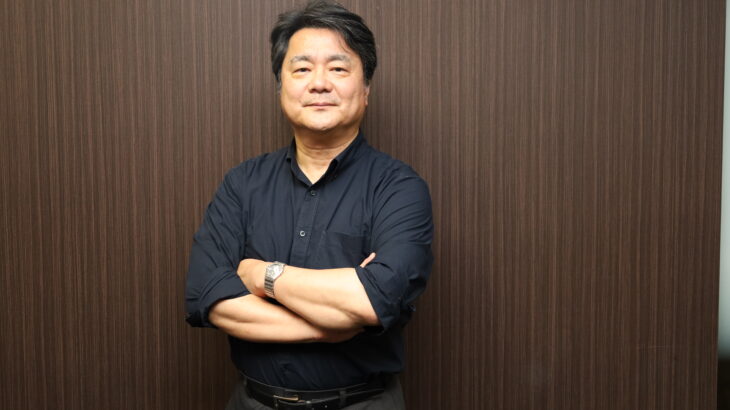【第2回 2次試験対策の勉強会がティッピングポイント】
過去の記事:第1回

育児の時間と家族の時間を考え、会社員から個人事業主に転身した中川千春さん。仕事を進めていく中で、もっとお客様の役に立ちたいという思いから中小企業診断士の受験を決意し、2年間の受験期間を経て、2023年度に合格する。第2回は、受験時代の勉強方法を伺った。
1次試験対策は、過去問の繰り返し学習
中川さんの受験歴は、1次試験が1回、2次試験が2回の2年間である。1年目は、1次試験および2次試験とも、市販の教材を使った独学である。2度目の2次試験では、2次試験対策の通信講座を利用した。
1次試験科目の7科目のうち、「特定の科目が苦手だったと感じたものはない」という。但し、経営情報システムと経営法務は、過去問を解いた年度によって、取り組みやすかったり、取り組みにくかったりして、点数にバラつきが出ていた。それ以外の科目は、「勉強の当初は点数が低いけれども、勉強を重ねるにつれて、過去問の点数が上がっていった」と回想する。「1次試験は、覚える範囲が膨大で、何度も過去問を解いても間違える問題があると、『自分には向いていない』と、あきらめそうになった」と当時を思い出しながら話す。1次試験の勉強は、過去問の繰り返し学習を通じて、知識を深め、間違ったところはテキストを参照して理解を深める。また、YouTubeの動画で、解説が公開されてものも活用して知識の定着を図り、1次試験を突破した。基本通りの勉強法で特別なことはしていない。しかし、強い意志は必要だ。
2次試験対策、勉強した時間と成果にギャップ
2次試験の事例Ⅳは、難しいものの、時間をかけることで、少しずつ前に進んでいる感触は得られた。「大変でしたけど、もう少し前に進もうという気持ちになった」と頷く。事例ⅠからⅢは、演習問題や模試を解いても、費やした時間に対して必ずしも比例して点数が伸びない部分があった。「最初の勉強スタート時期から見ると少しずつ良くなっているけれども、『向き不向きがあるのかな』と思うほど、伸びのペースが上下した」と話す。「事例対策を『どうやったらいいのだろう』と、2次試験対策中は、スランプになることがあった」と振り返る。
通信講座の仲間との勉強会が成長の鍵
2次試験対策の通信講座で出会った仲間との勉強会が、ティッピングポイントとなった。本人は、「完全にスランプを克服しましたと言い切れないけれども、同じ通信講座を受けているメンバーの勉強会に参加したことは、とても良かった」と語る。
通信講座の受講生の一人がSNSを通じて、「同じ通信講座を受けていて、且つ、2回目の挑戦となる人」という条件のもと、勉強会の参加者を募っていた。「参加したい」と声をあげ、勉強会に加わった。リモート会議ツールを使った話し合いやチャットツールを使って答案用紙を共有して、お互いの都合が合うタイミングでコメントを回答する方法で開催された。無理なく継続できるスタイルの勉強会だった。 模試の結果に対して、仲間から第三者の視点として意見をもらった。通信講座の回答解説の冊子や動画をもらって復習をする場合に比べて、同じ受験生同士の視点は、気づかされる部分がいくつもあった。「お互いの答案をみて、『あっ、自分にはここが足りていなかったな』と気づく。直接コメントをもらわなくても、『今度は、この着眼点を取り入れよう』と考え、『どうしてこの人はこのような答案を書いたのか』を推察した」と、客観的に答案を見る機会が刺激となった。また、仲間にコメントやフィードバックをする過程で、「どのように伝えたら適切に伝わるか、伝えた相手が、よりよい成果を出すにはどうするとよいか」を意識することで、自分も成長できた。

石川 達也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
東京都練馬区在住。2017年10月中小企業診断士登録。コンピュータメーカーおよびITシステムベンダーで、法人営業とサービス企画に従事。その後、経理や取締役の意思決定支援にかかわる管理業務にキャリアチェンジ。現在は、計量器販売の中小企業に勤務し、経理、人事と社長の特命業務を担当。「汗を共にかき、輝く未来を分かち合う」をモットーに、企業内診断士として活動中。