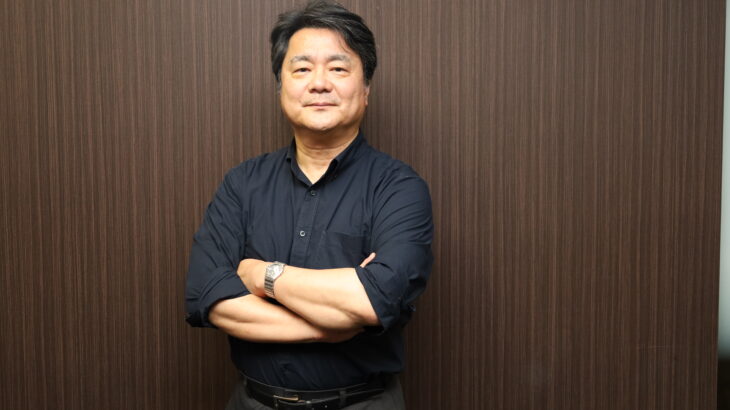【第2回 「どのような問題でもこのパターンで対処する」】
過去の記事:第1回

1次試験には1回目で合格したものの、2次試験には3回目で合格した加藤裕之さん。2次試験突破に向け、多くの受験生が直面する課題を、加藤さんはどうやって乗り越えたのか。第2回は、技術面、心理面の両面から2次試験の突破法を描く。(以下、敬称略)
つかみどころのない試験
「2次試験は何がなんだかわからないうちに終わったというのが正直な気持ちだった」
受験勉強を始めた1年目は、得意科目が財務・会計のみだったこともあり、「1次試験集中型」で臨んだ。1次試験が終わってから始めた2次試験の勉強は、後で思えば、過去問をやみくもに解いていたに過ぎない。結果は予想できた。さて、2回目の受験に向けてどうするか。
1次試験の知識と与件文をインプットに、できる限り高得点を期待できる解答を生成するプロセスが必要だった。やみくもに過去問を繰り返すだけでは、次も2次試験は突破できない。
解答プロセスを磨く
まずは情報収集。1年目から通っていた大手資格予備校の講師や知り合いなどから情報を集め、2次試験対策専門校で「これだ」というものを見つけ、事例Ⅰのみ受講する。事例Ⅰが特に苦手だったことと、解答プロセスは事例Ⅰ以外のⅡやⅢでも共通だと考えたからだ。
段落番号の付け方や試験問題用紙の余白ページの使い方、時間配分や設問文の主語・時制・レイヤーの識別、与件文の分析方法など、手順書を作って、しっくりするまで模索した。
「不合格で落ち込むというよりも、解答プロセスを固めることで今までと変わるという期待感の方が大きかった」
最後まで試行錯誤したのは、与件文の分析でマーカーを使うかどうかだ。
「2次試験対策専門校のSWOTをマーカーで色分けする方法をやり切る自信がなかった。2回目の2次試験まではマーカーを使わず、シャープペン1本でやっていた」
しかし、2回目も不合格。自信を持ってやれる解答プロセスが必要だと思った。解答プロセスについて書いた本を探すうちに、設問と関連する与件文の箇所にマーカーを引く方法を解説している「30日でマスターできる 中小企業診断士第2次試験 解き方の手順(中央経済社)」という本に出会った。これでやっと自分なりの解答プロセスに絞り込むことができた。
振り返りで、着眼点・文章力を磨く
2回目の2次試験が不合格となった時、加藤は「マズイ」と思わず呟いた。
「同じことをやっていたら変わらない。ショック以上に、このままではいけないという気持ちが強かった。途中で諦めるのが嫌い。すぐに次も受けると決めた」
加藤のギアがもう一段上がる。先に書いたマーカーの使い方以外に何が問題なのかを考えた。加藤は2次試験の再現答案を「ニュアンスを書き留める程度」にしか作っていないことに思い当たった。過去問や模試も含めて、「ある意味書きっ放し」。着眼点や文章表現、解答プロセスの振り返りができていなかったのだ。
そう気づけば、加藤はすぐに行動に移す。「ふぞろいな合格答案(同友館)」や2次試験対策専門校が開催する2次試験対策セミナーに参加し、自分と他者の答案や解答プロセスを比較することで、手順書にフィードバックし、着眼点や文章力を磨いていった。
自分を安心させる拠り所
多くの合格者が受験後に「全く自信がなかった」と述べている。加藤も3回目の受験の後、「ちょっと無理かな」と感じていた。今、振り返って、つかみどころのない試験で合格を勝ち取れるかどうかは、自分なりの解答プロセスを作れるかどうかだと確信している。これが定着してくると、着眼点のバリエーションを増やすことや採点者に意図を的確に伝える文章力を磨くことに重心が移せる。
「どのような問題がきてもこのパターンでいくと思えるようになると、ある種の安心感を持てる」
加藤は過ぎ去りし日を懐かしむように、そして自分に言い聞かせるように言った。

前田 浩光 取材の匠メンバー、中小企業診断士
“共感経営”ナビゲーター。社員・ステークホルダーの共感を呼ぶ経営をナビゲート。大手製造業で主宰した多数の小集団活動プロジェクトで、品質・生産性向上を実現。何よりもメンバーが変容し、生き生きと成果に結びつける姿に感動したことが、中小企業診断士を志すきっかけに。(公財)日本生産性本部のコンサルタント養成講座を修了し、2023年4月に独立開業。“共感経営”を実践する企業を一社でも多く生み出すことを目標に活動。