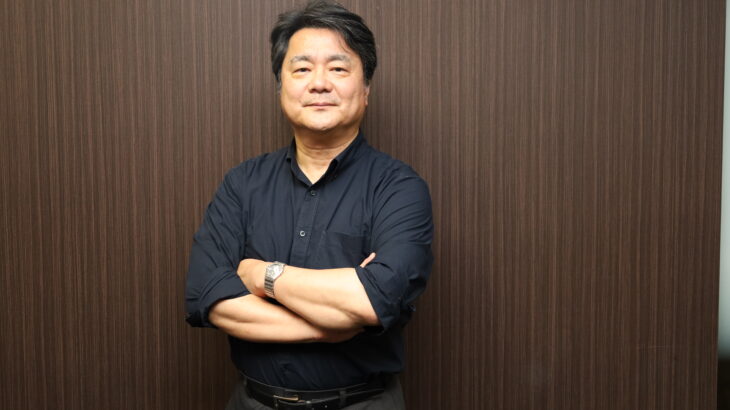【第2回 診断士試験の改定をはさんだ資格取得への道のり】
過去の記事:第1回

金融機関において数多くの職種を経験してきた小松さん。中小企業診断士資格取得への挑戦は現在の診断士資格試験制度への移行する以前の1999年にさかのぼる。現在の制度で2020年に2次試験挑戦に至るまでの軌跡を紹介する。
旧制度の下での1次試験合格
中小企業を主な顧客とする金融機関に入社したために、中小企業診断士という資格については目にすることが多かった。自然と自分も早く取得したいという思いを持ち、社内の中小企業大学校への国内留学制度に応募したが、あえなく落選。そのあとすぐにほどなくして当時の経済企画庁へ出向となり、2年間をそこで過ごすことに。国際経済を担当することになった1年目は経済審議会で長期経済計画策定の年にあたり、その策定を支援する業務に携わることになったため目まぐるしく多忙な日々を過ごす。診断士資格については頭の片隅にあったものの、取り組む時間的余裕がなかった。2年目になり、すこし落ち着いてきたことを機にここはチャンスということで一気に1次試験の勉強に集中し、1999年夏の試験で合格することができた。
当時の診断士試験は商業、工業、情報の3部門のうちどれか一つを選択して受験するというしくみで、現制度に比べれば狭い範囲ながら深い知識が問われ、一発合格を前提とする試験制度であった。2次試験のストレート合格は早々にあきらめて、試験対策を考えていたところ2000年に中小企業指導法が中小企業支援法なって、2001年からの中小企業診断士試験制度が大きく変更。移行措置として期限の定めなく、2次試験をあと1回受験できることになった。
一念発起しコロナ禍での2次試験へ
出向から復帰して、社内の様々な部署での業務に打ち込み責任も重くなっていく中、集中して勉強時間を捻出しにくい環境で、中小企業診断士の2次試験受験に対する意識は薄くなっていった。
時は流れ2020年、世界はコロナ禍に見舞われる。同時期にグループ会社へ出向していた小松さんは一部在宅勤務もできるようになる。それまで時間が止まっていた中小企業診断士2次試験への挑戦を一念発起。とはいえ、それまで二十年近く前に合格した1次試験の知識はもはや記憶になく、さらに制度が大幅にかわってしまい自分が勉強したこともない領域も多く存在するという厳しい現実に直面する。
それでもとにかく最初の一歩を踏み出すべく、「中小企業診断士2次試験合格者の頭にあった全知識(同友館)」を購入し、さらにTACの2次試験対策講座の受講を決めた。授業を受けていくうちに明らかになったのは、2次試験の四つの領域の中で、事例Ⅳは得意領域として取り組める一方で、事例Ⅲに関してはまったくの門外漢である、ということ。2次試験の日まで時間がない中で事例Ⅳで高得点を確保し、不得意科目の事例Ⅲをカバーするという戦略をたてる。
早朝時間と通勤時間を利用しての2次試験対策
コロナ禍の緊急事態宣言により、TACもオンライン授業となってしまい、通信教育と同じ環境でのモチベーションの維持に苦労する。そこでまず勉強時間の確保に早朝起床で2時間ほどを充てた。また、出社の際には2次試験解答のコツをつかもうと通勤中にTAC過去問動画などを視聴。 広報部に5年ほど在籍している時期に、広報誌や社内報、プレスリリース等の校正を行っていた経験や、それまでの中小企業融資の現場経験から事例Ⅰと事例Ⅱでは相応レベルの解答文を導き出せるという感触を持てた。あとは事例Ⅳでいかに高得点をたたき出し、事例Ⅲをカバーできるか、にかかっていると判断した。やがてコロナ感染の落ち着きによって週末にはTACの自習室にも通うことが可能になり、他の受験生の熱気を身近に感じながら自分を叱咤激励し勉強を重ねていった。

菅野 靖雄 取材の匠メンバー、中小企業診断士
東京都在住。大手電気メーカーの事業部門で経営管理業務を長く勤め、海外駐在経験も豊富。業務経験の体系化を目的に2023年度の中小企業診断士2次試験に合格。企業内診断士としての活動を通じ中小企業診断士ネットワークを拡大中。