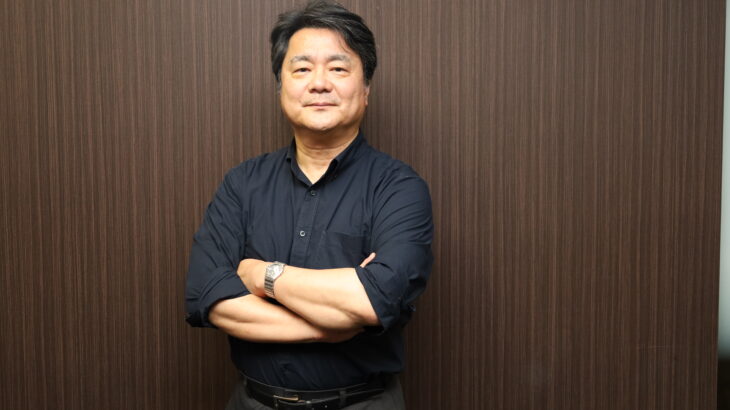【第2回 1次試験、2次試験とも独学で受験】
過去の記事:第1回

バイオテクノロジーの修士号を持つG.Mさんは、2000年に製薬会社に入社し、以来研究職として活躍されている。中小企業診断士試験は、2021年に1次試験に合格、2次試験は2022年の2回目の受験で見事合格。本稿では2次試験突破のコツをうかがった。
1次試験の財務・会計は94点
G.Mさんは、2021年に中小企業診断士試験へのチャレンジを始めた。この年、MBAコースで鍛えた財務面の知識で、財務・会計は94点という高得点で1次試験は軽々と突破。この勢いでいけば2次試験の事例Ⅳは得点源にできる、と考えていたそうである。
2次試験の1回目は「コテンパンにやられました」
しかし、2次試験の事例Ⅳ問題は思いのほか複雑で、しかも最終科目で疲れているところでパニックになってしまった。G.Mさんいわく「コテンパンにやられ、玉砕しました」。
1回目の2021年の受験では1次試験の勉強に集中し、2次試験の受験勉強に取り掛かったのが1次試験合格後だったので勉強時間が不足していたこともあり、1回目の2次試験は不合格に終わった。1回目の2次試験に不合格となった時に、2回目の2次受験も再び失敗した場合を想定し、1次試験を数科目だけ受験しておく人もいる。これは、1次試験で合格した科目は最長3年間の有効期限があることを利用して、例えば記憶系の中小企業経営・政策など苦労して記憶したものを忘れない内に受験しておき、次の1次受験の負荷を減らしたいためである。(1次試験の科目合格パターンについては、一般社団法人/日本中小企業診断士協会連合会のホームページを参照されたい)
「ここで落ちたらもう受験しない」覚悟の2年目受験
しかし、G.Mさんは2022年の受験では「ここで落ちたらもう受験しない」という堅い決意をもって臨む。1次試験の勉強は一切行わず、2次試験の勉強に集中したのである。これが功を奏し、2022年秋の受験で見事合格。ちなみにこの時の事例Ⅳは70数点獲得できたそうである。
1次試験、2次試験とも独学での挑戦
勉強方法は1次試験、2次試験とも独学で、1次試験ではひたすら過去問を解くことに集中した。1次試験はマークシート方式で正解が発表される。また、受験テクニック的には必ずしも100点を目指す必要は無く、各科目で40点以上、平均で60点取ればよいので、G.Mさんのように圧倒的な得意科目があると有利と考えられる。
ところが1次試験と違い、2次試験は記述式で公式な正解が発表されない。G.Mさんも2次試験は、過去問を見ても何が何だかわからず悩んでいた。そのとき「ふぞろいな合格答案(同友館)」という合格者の再現答案を集めて分析しているテキストがあることを知る。分析から導き出された採点基準も掲載されており、G.Mさんはそれを参考に自分で解いた過去問を採点して確かめることを繰り返した。それでも本当に何が正解か完全には理解できず、苦労したという。そこで採点基準としての利用に加え、「ふぞろいな合格答案(同友館)」を参考にして解き方の改善に取り組んだそうである。
2次試験過去問10年分をクリア
このように過去問と「ふぞろい」の活用を中心に2次試験対策を行ったG.Mさんだったが、1年目は時間がなく過去問も5年分程度解くにとどまった。2年目は集中して10年分をこなすことができた。ただ、何が正解かは最後までわからなかったという。
G.Mさんが診断士受験勉強を始めたのはコロナ禍中で、当時は在宅勤務も多く勉強時間が確保しやすかったことも幸いした。仕事が終わったら自宅近くのスターバックスコーヒーで勉強することを日課としてルーチン化できたので、それほど苦労せずに勉強のモチベーションを維持できたそうである。
次回は、G.Mさんの企業内診断士としての活動について報告する。

齋藤徹也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
半導体用フォトマスク、半導体用インターポーザ―、プリント基板、各種エッチング部品などの生産現場で、QCサークル活動、5S活動をはじめ、管理面では品質管理、生産管理、中期計画の作成などを経験。自社の10数工場で歩留まり改善、リードタイム短縮を指導した。退職後、2024年中小企業診断士登録。製造業の支援を中心に活動を模索中。東京都中小企業診断士協会三多摩支部所属。