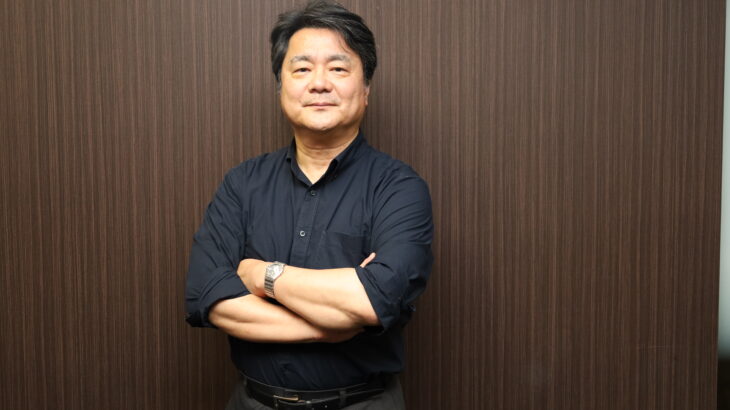【第2回 友人に打ち明け孤独感を解消する】
過去の記事:第1回

豊田さんは働き盛りの男性である。オンラインで取材を行ったが、やさしい笑顔と丁寧な語り口から実直な方と容易に想像できた。そのような豊田さんから中小企業診断士試験を受験しようと思った経緯から合格までの3年間についてお聞きした。(2回/3回)
引越先からの予備校通学
異動に伴い地方に引っ越した豊田さんだが、引越先から予備校まで高速バスで片道2時間を越える。高速バスは立って乗車はできないため、確実に座れるが長時間同じ姿勢は辛い。通学費用も往復で5,000円近くかかる。しかし、予備校に学費は既に払い済みであり、中小企業診断士の勉強は面白い。チャレンジをやめる理由はなかった。
乗り物酔いはしないタイプだったので、予備校までの移動時間は新たな勉強時間としてテキストを読むことにあてた。しかし、始めて学ぶことが多かったため、1回目の中小企業診断士試験は経済学・経済政策と経営情報システムの2科目の合格だった。
独学で1次試験合格
2年目は継続して都内の予備校に通うのではなく、自宅での独学を選択した。地方への引越に伴う生活の変化、バス通学の大変さを振り返り、自分のペースで勉強したかった。
また、手元にある予備校のテキストや問題集を継続して利用することで1次試験は合格点に到達できると判断したため、新しいテキストの購入や通信講座への申込は行わなかった。平日は早起きし朝1時間程度勉強し、帰宅後30分ほどランニングして、気分をリフレッシュさせた後に2時間程度机の前に座り、休日は10時間、週にすると30時間前後勉強した。
残り5科目の過去問や問題集を繰り返し解いて、必要な知識を身につけていった。1年目のテキストには授業中に気になったことをメモに残しており、理解を深めるために役にたった。
週間の勉強計画など事前計画はたてず、振り返りを重視し、勉強内容や勉強時間はスマートフォンのアプリケーションに記録した。自分がどのくらい勉強したかを把握することはモチベーションの維持につながった。地道な取り組みにより、2年目の1次試験は残りの5科目全てで60点を越え、2次試験に挑む権利を得た。
孤独感の解消
当初、中小企業診断士取得に向けて勉強していることは誰にも伝えていなかった。
1年目は周りの誰にも言わないで勉強した事ことにより孤独感は大きかった。孤独感を解消するため2年目からは、同僚や友人に勉強することを伝えた。ストレスを解消するために、月に1回程度同僚や友人と飲食をともにした。また、勉強の合間にラジオの好きなお笑い番組を聴いて気持ちをリフレッシュさせるなど、継続的に勉強をするための努力を怠らなかった。
孤独感は解消される一方で不安や焦りは残った。独学は勉強の進捗をはかるベンチマークとなる仲間もアドバイスを頂ける先生もいない。1次試験は通学の時の資料があったが、2次試験は完全独学である。自分の勉強方法は正しいのか、自己採点の基準はあっているのか、抜けている知識がないか、合格ラインに達しているのか、自身が想定した以上に不安や焦りはあったという。
1次試験合格後に2次試験の勉強を開始した。結果は不合格だった。受験直後もできたという感覚はなく、自己採点でもすべての事例で合格点に到達はしていなかったという。
3年目も独学を決意
中小企業診断士試験は2次試験に落ちても、1次試験に合格した翌年は1次試験が免除される。 勉強を始めて、3年目、2回目の2次試験に向けての勉強は前年と同じように独学での勉強を選択した。勉強の仕方も同じで市販の過去問をベースとした2次試験のテキストを何年分も解くというスタイルを継続した。

井部 雅章 取材の匠メンバー、中小企業診断士(登録予定)
2023年度中小企業診断士試験合格。他に簿記やIT関係の資格を有する。大学院卒業後、大手IT企業に就職し、20年近く同企業に勤める。当初はSEとしてシステムの提案、開発、運営管理支援などを行っていたが、営業に異動。営業としては公共機関向けにシステムの提案やシステム導入後のアフターフォローを担当している。