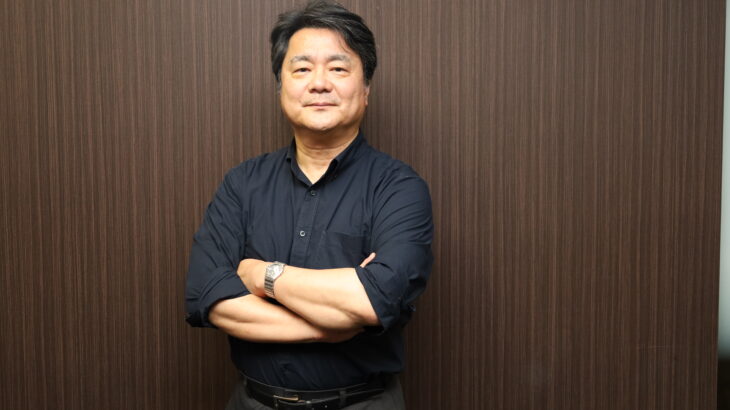【第3回 中小企業診断士の実務を学ぶ】
過去の記事:第1回、第2回

バイオテクノロジーの修士号を持つG.Mさんは、2000年に製薬会社に入社し、以来研究職として活躍されている。中小企業診断士試験は、2021年に1次試験に合格、2次試験は2022年の2回目の受験で見事合格。本稿では診断士資格取得後の活動と今後の抱負、受験生へのメッセージをうかがった。
フィナンシャルプランナー2級も取得
G.Mさんは中小企業診断士資格についでフィナンシャルプランナー2級の資格も取得している。診断士試験合格後、書店の資格関係のコーナーに立ち寄りフィナンシャルプランナーのテキストを手に取った。ざっと目を通すと、いままでの勉強で得た知識を活かせばそれほど勉強しなくても取得できそうだし、中小企業診断士の仕事にも役立ちそうだ、と考えて受験してみた。「実際、受けてみたら受かったという感じです」と、G.Mさんの財務面の強みがここでも活かされた。
実務従事を経て中小企業診断士登録
2次試験合格後、中小企業診断士として登録するためには15日間の実務補習または実務従事が必要である。G.Mさんは、就業時間との調整が容易な実務従事を2023年の夏季に受講し、同年11月に診断士登録した。
副業OKに
G.Mさんが所属する企業は、仕事に影響ない範囲で活動することを条件に副業を認めるようになり、上司に相談したところ「いいんじゃないか」と言ってくれたそうである。ただ、仕事を指示する立場として自分が副業しようとしている、とは部下には話しにくいと言う。
中小企業診断士としての実務の勉強
G.Mさんは、ヘルスケア分野での深い知識と経験を強みとして、診断士活動をしたいと考えているが、実際にそうした業務を獲得、活動するには中小企業診断士の実務がまだまだわかっていないことが弱みだと認識している。そこでG.Mさんは、この弱みを克服するため、2023年11月、中小企業診断士の登竜門と言われる東京都中小企業診断士協会中央支部のフレッシュ診断士研究会に参加、さらに国際部、地元の診断協会の新人支援の研究会、IT関係の研究会、講演・講師業に関する研究会などにも参加している。これらの活動は、実務能力を高めるためと、協会活動のなかで仕事の機会をつかむためで、他の多くの中小企業診断士も参加している。
これらの活動からは、「まだまだ仕事をする上で実力不足。いろいろ経験することが必要なので、やれる範囲で機会があればどんどん積極的に取り組んでいきたい」と言うG.Mさんの言葉通りのアグレッシブな姿が見えてくる。
企業内診断士としての「型」を作りたい
今後の活動についてG.Mさんは、独立は考えていないが、今後5年くらいかけて企業内診断士として無理のない範囲で、資格を活かして顧客価値を満たし収入になる「型」を作り、定年退職後には中小企業診断士活動中心で一定の収入が確保できるようにしたい、と考えている。
G.Mさんは、本稿第1回でふれた新規事業開発の経験は、中小企業創業者の立場が理解できるようになったこと、協業相手が破綻したことを含め、今後の中小企業診断士活動の強みになると考えている。
診断士受験生へのメッセージ
最後に、受験生へのメッセージをうかがった。G.Mさんは、「中小企業診断士の勉強は、始めるまではやろうかどうしようか悩む人も多いと思う。ただ1回やり始めると意外とのってきて、新しい知識が得られ楽しいことも多い。もちろん試験なので受かるかどうか先が見えず、つらいことや苦しいこともあるが、楽しみながら受験して合格すれば活躍の場となる非常に大きな世界が待っているので、迷わず飛び込んでほしいなと思います」とのことであった。

齋藤徹也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
半導体用フォトマスク、半導体用インターポーザ―、プリント基板、各種エッチング部品などの生産現場で、QCサークル活動、5S活動をはじめ、管理面では品質管理、生産管理、中期計画の作成などを経験。自社の10数工場で歩留まり改善、リードタイム短縮を指導した。退職後、2024年中小企業診断士登録。製造業の支援を中心に活動を模索中。東京都中小企業診断士協会三多摩支部所属。