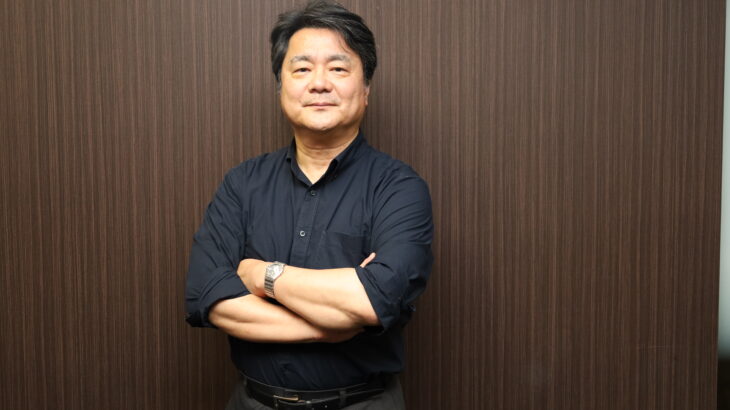【第2回 隙間時間を捻り出す】
過去の記事:第1回

大野秀敏さんは、2021年の夏から中小企業診断士の勉強を始め、2022年の1次試験および2次試験にストレート合格した。当初は1次試験が何月にあるのかも知らず、「興味を持った時には既に1次試験が終わっていた」という。それでもすぐに参考書を買いそろえて試験勉強に取り組んだ。
学習は親しみのある科目から
企業経営理論、財務会計、運営管理などから学習を始めたところ、企業に勤めていた頃の実務経験からスムーズにスタートできたという。
「これから勉強を始める方には、最初に躓かないためにも、実務で経験がある科目や親しみがある科目からスタートするというのも良いのではないか」と大野さんはいう。
ひたすら知識定着を念頭に試験対策を行ってきた大野さんだが、1次試験が終わった段階で2次試験の準備は全くしていなかったそうだ。
「2次試験のことは1次試験に受かってから考えようと思っていました。自己採点をしたら合格点をクリアしていたので、慌てて2次試験について調べました」
2次試験対策は業務知識の延長線
その後、2次試験の準備は約2ヶ月という短期集中でストレート合格をはたした。その要因は何であったのか。
「もともと仕事でプロジェクトマネジメントや事業企画をやっていました。2次試験の内容はさらに実務に近い領域だったので、スムーズに出題の趣旨が頭に入ってきたのだと思います。また、企業に勤めていた時に2年間にわたって大学院に国内留学をさせてももらい、経営戦略やイノベーション論などについて学んだことなども良かったのだと思います」
大野さんにとっての2次試験対策は、いきなり高い壁に挑戦というものではなく、業務で得た経験知の延長線上にあるものだったのであろう。中小企業診断士の試験では、会社員の経験や学んだことが活かせるというのはよく聞く話である。企業で長い間経験を積んだ50歳代以上の受験者は、少なからずアドバンテージがあると考えて良さそうである。
「中小企業診断士の勉強は、これまで長い間、実務で行ってきたことの答え合わせになりました。間違って理解していた知識や理論を補充したり、補正したりできたことは良かった」と大野さんはいう。
多くの50歳代以上の人たちにとって、中小企業診断士の試験にチャレンジするということは、ある意味で長い社会人生活の振り返りに近いことなのかもしれない。
いかにして時間を捻出するか
一般的な話だが、50歳代になると社会での役割も大きくなる。同時に付き合いやアフターファイブの誘いも増え、勉強時間の確保が困難になるものである。この点について大野さんは、「私の場合は、家族のコミュニケーション時間とのバランスや、本業である大学業務、研究時間などへの影響を乗り越えるための時間の確保が大変でしたね」という。
この課題を乗り越えるためには、「いかにして隙間時間を捻出するか」が重要なのだそうだ。
「まずは、その数分が隙間時間であることに気づくことが重要。『この3分って無駄じゃない?』みたいな時ってありますよね。これをたった3分と思ってしまうとそれまでですけど、例えば1次試験の過去問であれば、3分あれば1問や2問はできる」
大野さんにとって、隙間の3分とは、朝起きて布団から出るまでの時間であったり、レジの行列に並んでいる時間であったり、通勤時間であったりと、あらゆるところから捻り出すものだったのである。
「隙間時間を有効に活用するために過去問などをすべてスキャンし、タブレット端末でいつでもみることができるようにしていました」という。
画面の大きいタブレット端末というのが重要である。なにしろ「悲しいかな、50代になるとスマートフォンでは字が小さくて読めない」と大野さんはいう。同じく50歳代の筆者も全く同感である。

岩水 宏至 取材の匠メンバー、中小企業診断士
製薬企業に30年あまり勤務し、営業、マーケティングおよび海外事業にかかわる。出向した海外子会社で経営立て直しを経験したことから、中小企業の経営支援に興味を持つようになる。2023年に中小企業診断士登録し独立開業。現在は中小企業の経営支援、事業承継支援などを行っている。座右の銘は「人間到る処青山有り」。