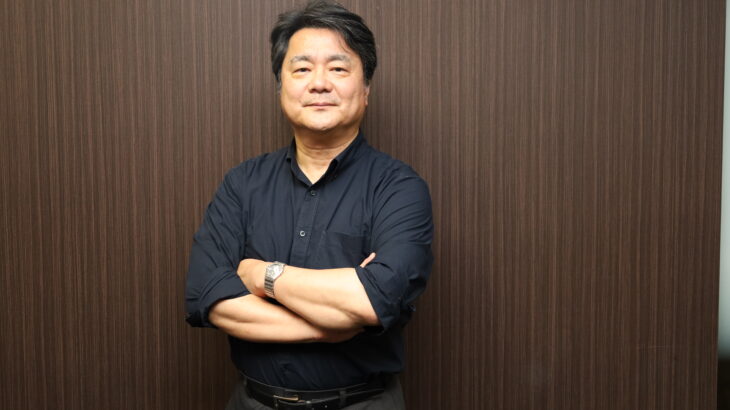【第2回 中小企業診断士合格にむけて】
過去の記事:第1回

T・Kさんは管理職から専門職への異動をきっかけに、中小企業診断士をめざすことになった。機械設計から生産管理、生産技術に異動してからデータを確認し、遅延改善させる等、QCDを意識するようになった。2020年の1次試験合格に向け猛勉強を続けていたが、結果は期待通りのものではなかった。そんなKさんのその後について取材した。
挫折からの復活
2020年の1次試験の不合格はKさんにとって、精神的に辛いものであった。そもそも中小企業診断士は簡単にはなれないと思い、受験勉強をやめようと考えたこともあった。そんな中、Kさんにとってうれしい出来事が訪れた。孫の誕生である。しかも双子の女の子であった。Kさんは大いに喜び、1次試験不合格の精神的なダメージは吹っ飛んだ。またKさんは「楽しいことは年1個あればいい、2個はいらない」と不合格を受け入れることができ、再び中小企業診断士への道を歩き始めた。会社もビジネスキャリア構築を推奨しており、その一環として運営管理に似たような試験を受験した。
そして2021年8月に不合格であった財務、経営法務と、得意科目の運営管理を加えた3科目で、3回目の1次試験に挑んだ。孫たちの応援も力になり合格した。不得意であった財務は、前回の44点から88点にまで倍増させた。
2次筆記試験の不安
中小企業診断士合格までのプロセスとしてKさんは、1次試験2回、2次試験2回受験の計画を立てていた。しかし1次試験が3回受験となったため軌道修正し、2次試験は一発合格で挑んだ。2次筆記試験の勉強は1次試験と同じ学校のカリキュラムを受講していたが、理解不足もあり半分程度しかできなかった。苦手な事例Ⅳについても、カリキュラムの他に、受験生がよく使用する参考書を少し読む程度であった。Kさんはこのような勉強状態では合格は難しいと感じていたが、その通りの結果となった。
新たな出会い
2次筆記試験は再挑戦ができるので、来年の合格をめざして歩を進めた。半分程度しかできていなかった資格の学校のカリキュラムを、きちんと最後までやれば大丈夫だろうという楽観的な考えと、これで本当によいのかという不安が混在していた。結論として、このままではダメであろうと一念発起し、2次筆記試験対策の勉強法について再検討した。
SNSを中心にインターネットの情報から2次筆記試験の勉強法を探していると、別の学校のサイトに辿りついた。その学校では録画したものを視聴する形式ではなく、双方向のオンラインで、初対面の受験生同志でディスカッションをして正答を導くという、今まで経験したことがない勉強法であった。

上杉 嘉邦 取材の匠メンバー、中小企業診断士
京都府長岡京市在住。鳥取大学工学部物質工学科を卒業後、外資系大手製薬メーカーにて医薬情報担当者として約7年、医薬品開発業務受託機関で臨床開発モニターとして、約15年間勤務する。2023年1月によしくに中小企業診断士事務所を開業。医療系に強い中小企業診断士として中小企業の経営相談、経営改善計画書策定、人事評価制度制定、健康経営支援等、業種業態問わず幅広い分野で活躍する。