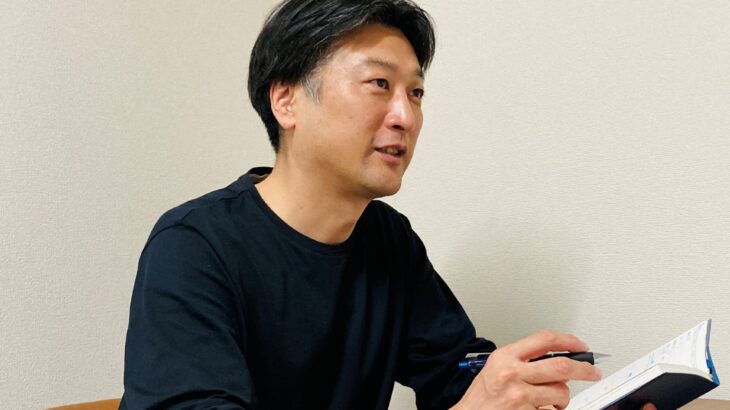【第1回 なぜ養成課程を選んだのか】

「養成課程を選んだことは全く後悔していないです」
中小企業診断士養成課程(以下、養成課程)受講を経て、現在スタートアップ企業のコーポレート部門で幅広い業務に従事しながら自身の活躍の場を模索しているK.Iさん。第1回では、なにを求めて養成課程を選択したのか、描いていたビジョンに迫る。
自分の可能性を探して
現在はスタートアップ企業で活躍しているK.Iさんだが、複数回の転職を経験している。経歴の多くを占めるのは知的財産に関わるキャリアだ。元々技術に興味があり、技術を守って価値や利益を生み出すことに貢献したいという自身の希望と合致していたのが知的財産の仕事だった。
そのキャリアは特許事務所でスタートした。仕事そのものは面白かったが、顧客の依頼に応えて権利を取得する業務に取り組んでいる間に、事業会社が権利をどのように活かしているのかを見てみたいという思いに駆られた。
「ただ、次に行った事業会社が属する業界は技術の進歩が早く、権利を活かすことがとても難しい業界でした。知的財産の仕事だけでは私が提供できることがあまりないと考えて、自分の幅を広げる必要性を感じました」
幅を広げる選択肢の一つが、中小企業診断士の資格に挑戦し、会社の経営への知見を広げることだった。
選ばれた中小企業診断士受験
会社に依存しない働き方ができるようになりたいという考えは元々もっていたのだと言う。その足掛かりとして資格取得が選択肢に浮かんだ。知的財産に関わる資格として知られているのが、弁理士だ。K.Iさんも弁理士資格の取得を考えたことがあると語る。
「弁理士の勉強は結局しませんでした。基本的に弁理士で活躍されている方は理系の修士や博士の方が大半という環境です。そこで文系のバックグラウンドをもつ私が活躍するビジョンが見えなかったということが要因です」
一方で中小企業診断士に対しては、明確な目標を立てることができた。それが資格取得に向けたモチベーションになった。知的財産を経営に活かすため、また、当時所属していた会社での知財部の価値を上げるために、知的財産と経営をつなげられるような知見を得ることを目指して挑戦を決めた。
中小企業診断士登録までの道のりは長い。だからこそ、知識獲得に留まらず、その知識をどう活かしたいかというビジョンを描いて、それに価値を見出すことが大事だ。K.Iさんは受験を検討する人へのアドバイスをそのように語った。まさにK.Iさん自身がそのような受験生であった。
求めたスタートラインへ
2次試験の受験はほぼ考えなかったに等しいと語るK.Iさん。紙面上で行われる2次試験と登録に必要な15日の実務経験だけでは得られないものを養成課程に求めたからだ。K.Iさんには、企業の問題を見出し、解決策を提案して対価をもらう経験がなく、その活動イメージが湧かなかった。リアルな人間を相手にしたとき、中小企業診断士試験受験のために学習した知識をどのように使えるかという経験まで試験勉強の過程でしておきたいと考えていた。K.Iさんが求める経験を得るには15日という時間は短かった。だからこそ一つの案件に時間をかけて取り組むことができる養成課程を選択した。
「養成課程の診断実習は、1社に1か月から1か月半かけて行います。時間をかけて、既に活躍されている中小企業診断士の方が出すような成果物を作り、それを見てもらうという経験を欲していました。密度濃い経験をしたうえで、中小企業診断士としてのスタートラインに立ちたかったという思いがありました」
K.Iさんは強い意志とビジョンをもって養成課程への挑戦を選んだのだ。

毛利 和裕 取材の匠メンバー、中小企業診断士
1993年生まれ。大阪市在住。大学卒業後、スポーツ用品メーカーに入社。営業職を経て、現在経理財務部に所属。連結決算や管理会計、開示書類作成など幅広い業務に従事。自身のレベルアップを目指して中小企業診断士試験挑戦を決意。1年弱の勉強期間で2020年度に中小企業診断士試験合格、2022年登録。大阪府診断協会所属。協会活動中に行ったプレゼンの好評価に自信を深めている。中小企業診断士として自身が情熱を注げる活動を模索中。