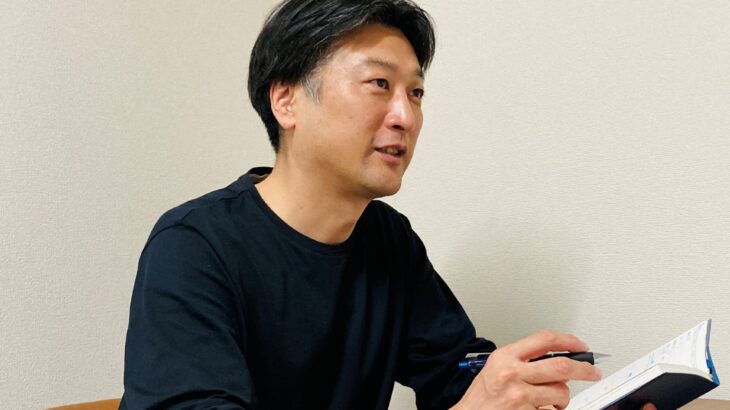【第1回 中小企業診断士を目指すきっかけと養成課程受験への挑戦】

ソフトウェア開発のプロジェクトマネージャーとして働きながら、中小企業診断士養成課程(以下、養成課程)を卒業し、2024年に中小企業診断士として登録した清水一茂さん。第1回は、中小企業診断士を目指すきっかけと養成課程受験への挑戦を語ってもらった。
憧れを現実に
清水さんが中小企業診断士を目指したのは、プロボノ(スキルを活かしたボランティア活動)を通じ、中小企業支援を行った際に感じた無力感がきっかけである。清水さんは当時、ソフトウェア開発のプロジェクトマネージャーとして働いていたが、自身の専門知識が企業支援にはほとんど通用しないこと痛感した。
しかし、同じチームとして企業支援を行った中小企業診断士がリーダーシップをとり、方向性を示し、具体的な施策に落とし込んだという。「中小企業診断士の資格を取ったらその人みたいになれるのではないかという憧れですね」と語る清水さん。
この経験がきっかけとなり、企業の力になるために、中小企業診断士の資格を取得したいと強く思うようになったという。
診断士試験の挑戦
1次試験、最初の年は3ヶ月前から対策を始め、経営情報システム1科目だけ合格した。本腰を入れて勉強をするため、図書館を利用し一人で勉強をしていた清水さん。すると、開いていたテキストを見て「中小企業診断士を目指しているのですか?」と声をかけられる。聞くと中小企業診断士試験の勉強会を開いているとのこと。これが今後の人生にも大きく影響する出会いとなる。
清水さんは勉強会を利用し、1次試験の勉強に臨む。苦手な経営法務は司法書士の資格を持つ仲間のサポートが役立った。自身はITを苦手とするメンバーに経営情報システムを教えていた。得意な科目を教え合い、補完し合いながら勉強することで、モチベーションも上がるという。
勉強を始めて3年目、ようやくすべての科目に合格し、晴れて1次試験を突破した。
養成課程への決意
中小企業診断士になるためには、1次試験合格後、2次試験に合格するか、養成課程を修了する必要がある。清水さんは当初、2次試験の合格と養成課程の受験の両方を検討していた。しかし、東洋大学の説明会で話を聞き、養成課程受験に専念することを決意する。
「説明会で話された教授が魅力的でした。うちに来たらどんなメリットがあるか、切磋琢磨して卒業すれば中小企業診断士としてのスタートラインに立てる、などポジティブに語られたのが印象的でした。」
また、カリキュラムが他の大学よりコマ数が多かったため、その分欠席できる日数が多く、卒業が現実的だと感じた。
「東京の大学で学食が一番美味しいことも決め手になった。」と笑いながら話す清水さん。
数ある養成課程の中でも東洋大学一本に絞り、準備を進める。具体的に行ったことは、研究計画書の作成と面接対策だ。特に研究計画書の出来栄えが合否を左右する。
東洋大学には組織論を専門とする教授がいるため、「プロジェクトマネジメントがなぜ失敗するか」組織論の観点から研究したいと思い立ち、研究計画書を書き進める。また、想定問答集を作り、面接の練習を行う。これらを1次試験終了から10月の養成課程の受験までの約1ヶ月の間に準備をしなくてはならないタイトなスケジュールであった。
これを乗り越えることができた理由は2つ。
1つ目は、持ち前の調整力を活かし、仕事を調整し、養成課程受験の準備の時間を作ったことである。そして2つ目は、診断士試験の勉強会でできたご縁である。勉強会メンバーで、大学院へ進んだ人がいたため、研究計画書のレビューや模擬面接の練習をしてくれた。試験当日、ブラッシュアップされた研究計画書を携え、面接の回答も完璧だったという清水さん。見事、養成課程合格を掴んだ。

長山 萌音 取材の匠メンバー、中小企業診断士
1993年生まれ。神奈川県出身。東京都在住。IT企業にてサーバーエンジニアとして勤務した後、Webマーケティング会社にてWeb集客に従事。その後、デジタルマーケティングのコンサルタントを経て、2023年に勢いで独立。東京都中小企業診断士協会城東支部所属。趣味はディズニーのグッズを集めること。(推しは『ピノキオ』のフィガロ)