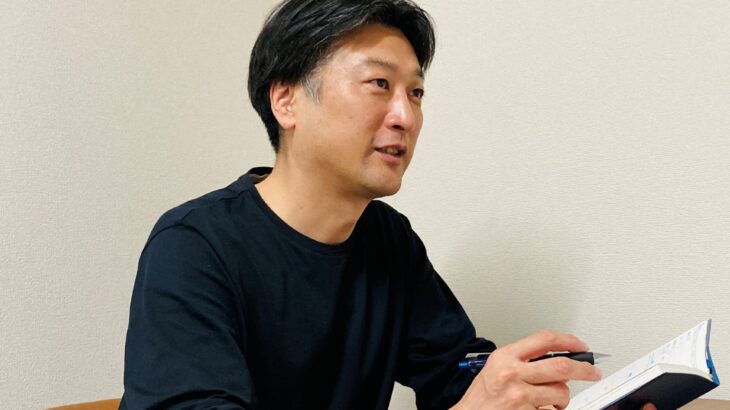【第2回 養成課程で得たもの】
過去の記事:第1回

「養成課程を選んだことは全く後悔していないです」
中小企業診断士養成課程(以下、養成課程)受講を経て、現在スタートアップ企業のコーポレート部門で幅広い業務に従事しながら自身の活躍の場を模索しているK.Iさん。第2回では、養成課程での体験や養成課程を通じて得られたものに迫る。
経験が浅くても貢献できた
養成課程中はすべてが困難だったと語るK.Iさん。コンサルタントとして活躍している人や金融機関で中小企業支援に業務として取り組んでいる人などの経験豊富な周囲のメンバーに比べて、外部の会社に価値を提供する機会があまりにも少ないと感じていた。その経験がある人は、自身の経験や1次試験の知識を提案につなげることができていた。一方でK.Iさんは、どのような提案をしたらよいのか、なにを言ってよいのかということにも頭を悩ませることになった。
グループで課題に取り組む機会が多かった養成課程。実務経験が浅くても、グループの中で貢献できることはなにかを常に考え続けた。
「経験のギャップが埋まるとは思っていません。自分自身がどのような価値を出せるのか、自分にできることはなにか、できることを増やしていくためにはどうすればいいかを考え続けなければならないということは、養成課程が終わった今も思っています」
養成課程の診断実習では、報告書やプレゼンテーション資料の作成を行う。場合によっては提言内容に紐づくテンプレートを作成することもある。提案を形にするという場面に自身が貢献できる可能性を見出したK.Iさんは、スキルを発揮しグループに多大な貢献を果たした。「K.Iさんがいてくれて本当によかった」というメンバーの言葉がなによりの証明だ。
診断実習で見えたリアル
診断実習で5社を診たK.Iさん。印象的だったのは、その会社の哲学や経営者の描く自社の未来像が三者三様に制度に表れていたことだった。それぞれの会社と向き合うときに、会社を一括りにしたり先入観をもって見たりしてはいけないという学びになった。
例えば仲の良い会社を作りたいとき、サークルのような会社にしたいのか、家族のような会社にしたいのか、それで制度は変わってくるそうだ。
K.Iさんが提案する際に大事にしたことが、制度の根底にある哲学だ。それを守りながら会社をより良くするためにはどうすればよいかが最も大事だと考えていた。
「会社に寄り添って、今の状態でも実行できるような提案ができたのではないかなとは思います。再度会社を訪問した際、私たちが提案したことをカスタマイズして取り組んでいるとお伺いしました。役に立つような提案ができたなと実感しています」
K.Iさんが診断実習で感じたやりがいは、もう一つある。自分の会社のことをここまで調べてくれる経験がなかったという経営者の言葉を聞き、自分の会社を振り返る時間を取ることは簡単ではないと知った。第三者の目で、自身の会社を振り返る機会を提供すること。中小企業診断士が行う診断そのものに、大きな価値があるのだと気づかされた。
築いた人脈は続いていく
長期間にわたって取り組む養成課程において、メンバー同士のつながりはとても強い。養成課程が修了した現在は、困ったことを相談したらアドバイスをもらえるような仲間となっている。メンバー同士でなにかに取り組む活動は維持していきたいという話もあがっている。
さらに、K.Iさんが受講した養成課程では、横のつながりだけではなく縦のつながりも築くことができた。修了が近づいた際には、どこでどのような活動が行われているか、どのようなところから仕事の話がもらえるか、どこに顔を出していると人と出会う機会となるか、といった情報を得ることもできたのだという。 K.Iさんは経験や学び以外にも大きなものを得たようだ。

毛利 和裕 取材の匠メンバー、中小企業診断士
1993年生まれ。大阪市在住。大学卒業後、スポーツ用品メーカーに入社。営業職を経て、現在経理財務部に所属。連結決算や管理会計、開示書類作成など幅広い業務に従事。自身のレベルアップを目指して中小企業診断士試験挑戦を決意。1年弱の勉強期間で2020年度に中小企業診断士試験合格、2022年登録。大阪府診断協会所属。協会活動中に行ったプレゼンの好評価に自信を深めている。中小企業診断士として自身が情熱を注げる活動を模索中。