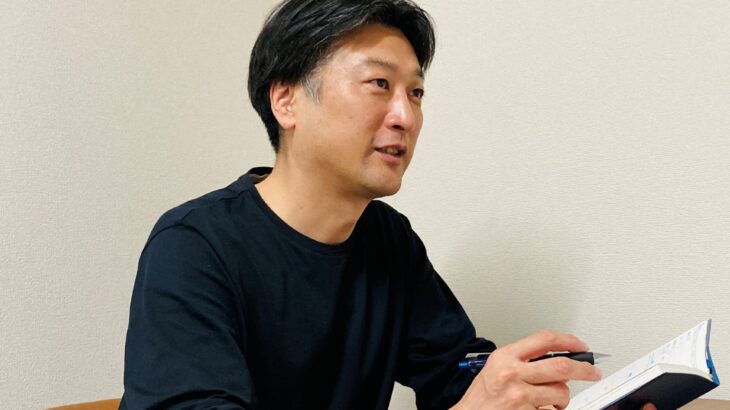【第2回 実習と修士論文に向き合う】
過去の記事:第1回

在京キー局で政治記者として活躍してきた田畑さん。東洋大学大学院中小企業診断士登録養成コースの入学試験に無事合格した。第2回では、養成課程での体験についてつづっていく。
リアル復活!キャンパスライフ
東洋大学大学院の養成課程は2年制である。社会人が働きながら履修しやすいよう、カリキュラムが土日と平日夜の開講となっているのが人気の1つだ。高い倍率をくぐり抜け、田畑さんは2021年4月に晴れて入学を果たす。通うのは、東京都文京区にある白山キャンパスだ。
当時はコロナ禍2年目。新型コロナウイルスの感染拡大と収束が繰り返されつつも、少しずつリアルが復活し始めた頃だ。60歳を目の前にして、どんな学生生活を送ったのだろうか。
「私はリアル中心で、ほぼ毎日通いました。座学の講義は基本土日で、平日夜がゼミでした。非常に知的刺激があって、厳しいながらも楽しかったです」と振り返ってくれた。
東洋大学大学院の養成課程で特徴的な科目といえば、「実習」と「修士論文」だ。この2つにフォーカスして取り上げていきたい。
対立は楽しい!?丁々発止の実習
実習は、延べ10日間を3週間から1か月かけて飛び飛びの日程で実施し、それが合計5回あったという。1回の実習ごとに、7~8人で1チームになり、インストラクターとして2人の先生がつく。学生各メンバーは「班長」のほか、「経営戦略」「組織・人事」「財務」「生産」「営業」など担当に分かれる。診断先の対象企業の規模や業種は様々で、田畑さんは、飲食業や製造業、流通業の診断を経験した。
「1回目の実習では、担当の先生に相当ダメ出しされましたよ」と田畑さんは振り返る。組織・人事パートを担当したものの、あまりに手探りで深掘りがなされておらず、相手先の求めるレベルに達していなかったという。じっくり1つ1つ議論して、求めるレベルに近づけていった。
実習では仲間同士の議論が活発化するが、紛糾することもたびたびあった。そんなとき田畑さんは、元“政治記者”の血が騒ぐようで、「意見対立にはどんどん自分から好んで首を突っ込んでいった方です」と笑う。かつて在京キー局への就職活動をした際、履歴書の趣味の欄に「議論」と書いていた田畑さん。『朝まで生テレビ!』ばりに、徹底討論するこのコースは、思いのほか水が合ったようだ。
修士論文では、学科最優秀賞を受賞!
大学院を修了するために必須となるのが修士論文。テーマはもちろん農業だ。田畑さんは、「農業における起業意思決定メカニズムの探索的研究」というテーマを設定し、出身地である富山の農企業の事例研究をしてまとめあげた。
修士論文を書くうえでのポイントは何だろうか。田畑さんは、指導の先生にいわれて印象的だったことを教えてくれた。「何も大発見や大発明をする必要はないよ。小さくてもいいから、何か1つ新しいことを発見、または発明して、社会に貢献する。これがアカデミズムですよ」と。つまり、誰もやったことのない何らかの研究をし、新しいフロンティアを見つけて切り拓かないといけない。それを悟った田畑さんは、日本語の論文を何十本と目を通す。しかし、「田畑さん、日本の国内の知見だけじゃ論文は書けませんよ。80億人を対象にした英語の論文から最新の理論を探してきてください」と指導教官からさらなる指摘を受けた。
久しぶりの英語漬けかと窮したが、田畑さんは一念発起した。翻訳機能を駆使しながら、2年間で100本以上の論文を読み漁った。未知の分野を深掘りしながら、アメリカの論文の中から今回のテーマに合う「土地への愛着理論」をみつけた。その理論を参考にして、日本の農業を考察したそうだ。日本の農業における新たな提唱ができたという。
そのかいもあって、田畑さんは学科最優秀賞を受賞した。苦労が報われ、喜びもひとしおだっただろう。評価ポイントは、提唱内容の進歩性にあったようだが、田畑さんはもう1つ理由をあげてくれた。「実はロジカルな論文に、詩をいれてみたんですよ」。論文の中で、農民詩人として著名な星寛治の詩を引用したそうだ。詩というエモーショナルな要素も使いながら、あるべき農業を主張したことで、他にはない論文に仕上がったことも評価されたのかもしれない。
いずれにせよ、修士論文を書くプロセスを経ることで、自分の知的可能性に挑戦できたことに加え、今後の自分の進むべき方向を整理することにもつながったようだ。この養成課程で得たものはとても大きい。田畑さんの充実した表情をみてそう感じ取った。
こうして2023年3月、田畑さんは無事に大学院を修了し、中小企業診断士の資格を取得することができた。

矢野 達也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
愛知県豊橋市出身、神奈川県横浜市在住。長らく食品メーカーのマーケティング部門で、事業戦略立案から商品企画・開発および広告・販促の実行まで幅広い業務に従事。現在は中小企業診断士として、副業やプロボノ活動で、主に中小企業の診断業務や執筆活動、自治体と組んだまちづくりアドバイザーなども実施している。趣味は食べ歩きやスポーツ観戦。クリケットやパドルテニスを楽しんでいる。