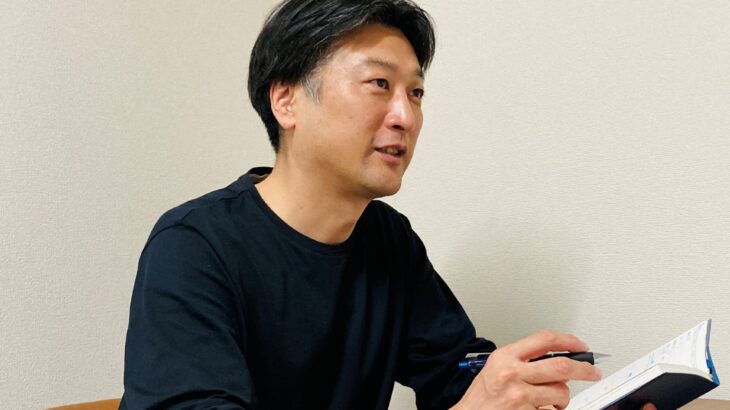【第3回 農業診断士として生きる】
過去の記事:第1回、第2回

東洋大学大学院中小企業診断士登録養成コースを経て、2023年5月に中小企業診断士に登録を果たした田畑さん。第3回は、養成課程の魅力と今後の自身の展望についてスポットライトを当てる。
養成課程後も生きる、仲間との絆
東洋大学大学院での2年間の養成課程を無事終了できてほっとしたという田畑さん。田畑さんにとって、養成課程の魅力はどのような点にあったのだろうか。
「やはり実習などを通じて、仲間との一種の“知的格闘”ができたことだと思います」と力強く語ってくれた。同期は様々な年齢や業種の会社員がいるなど多様性のあるメンバー構成で、いいところを学び合えたことが自分の成長につながったという。
チームでの議論では、あえて批判し合いながら、互いに学びを深める。大変ではあるが、同じ釜の飯を食った仲間との絆は、何物にも代えがたいほど強いものになったようだ。卒業した今でも、有志で月1回のペースで勉強会を開いて集まっているとのこと。確かに、中小企業診断士仲間の横のつながりを得られるのは、養成課程の良さの1つだろう。
他には、60歳を前に自分を相当追い込んで成し遂げられた経験も大きいと語る。限界を作らず自分で自分を乗り越えることができたという自信は、今後困難にぶつかった際でもあきらめずに挑戦を続ける糧となるにちがいない。また、パワーポイントやワード、エクセルに習熟した点も、田畑さん個人としてはこれからの実務上有用だと付け加えてくれた。登録後すぐに実践につなげられる点が、じっくり時間をかけて学べる養成課程の大きなメリットだといえそうだ。
自分に合う養成課程で飛躍しよう
どんな人が養成課程に向いているのか。田畑さんは2つあげてくれた。まず1つは「人とうまくやれる人」。チームでの活動が多いので、機能分化にもきちんと対応し、約束を守るなどきちんと順応できることが大切だという。あと1つは「知的好奇心の強い人」。とことん探求する姿勢が成果に結びつくといえそうだ。
今後養成課程を目指す方々へのメッセージを聞いた。「養成課程にも様々なコースがあります。短期間のコースもあるものの、その分密度が濃くなる。私は2年制でじっくりやるからこそカリキュラムを終えられたと思います。養成課程を選ぶ際は、ご自身に合うものをよく検討してみてください。応援しています」とエールを送ってくれた。
農業への思いで、つながる人脈
中小企業診断士になった今、田畑さんは精力的に活動を続けている。さらには、農業経営アドバイザー資格も追加取得した。目指すは“農業診断士”だ。
「日本人が100人いたら、作る人はたった1人で99人は食べる人。しかもその作る人は平均年齢70歳を超えるんですよ。あと10年経ったら一体どうなるのか。これってまずくありませんか」と日本農業の現状を教えてくれた。農業の魅力を伝えて若い人材を呼び込む。やがて食料自給率を引き上げ、日本の農業生産を安定化させたい。田畑さんは、大学院の養成課程コースで学んだことを生かして日本の農業を変えていきたいと意気込む。
農業経営者の会合や農業系の研究会に参加し、現場での課題を肌で感じながら、農業関係者との人脈を着々と広げている。
「最近出会いがあったんです」と田畑さん。農家の事業承継について考える有志の会があり、そのメンバーの中に弁護士の方がいて、自身を“農業弁護士”と語っているのを見つけた。それなら自分は“農業診断士”だ。思いをぶつけて意気投合するうちに、「農業士業の会を作りませんか」と行政書士などの士業仲間に広がって話しがまとまり、実際に発足したそうだ。農業の現場に赴き、様々な議論を重ねる日々は、田畑さんにとって本当に充実しているといえるだろう。
「不思議なもので、自分の志を持って動けば、人間同士は点にすぎないが、その点と点がシナプス結合のようにつながっていくんです。それが中小企業診断士の醍醐味だと思います」と最後に語ってくれた。このつながりが、きっと自分の未来を明るくしてくれるはずだ。
今後の田畑さんの活躍にぜひ期待したい。

矢野 達也 取材の匠メンバー、中小企業診断士
愛知県豊橋市出身、神奈川県横浜市在住。長らく食品メーカーのマーケティング部門で、事業戦略立案から商品企画・開発および広告・販促の実行まで幅広い業務に従事。現在は中小企業診断士として、副業やプロボノ活動で、主に中小企業の診断業務や執筆活動、自治体と組んだまちづくりアドバイザーなども実施している。趣味は食べ歩きやスポーツ観戦。クリケットやパドルテニスを楽しんでいる。