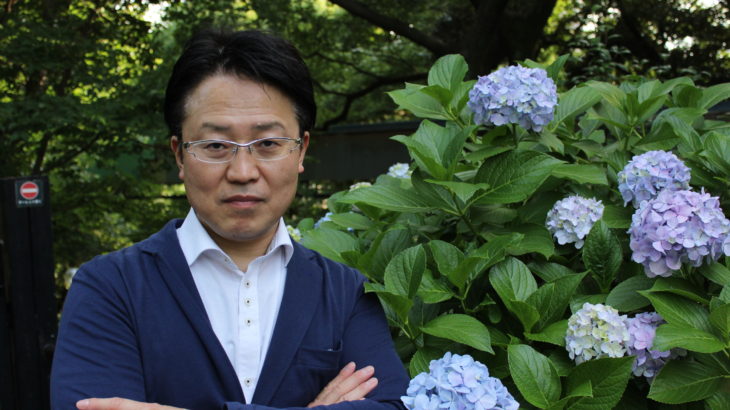【第3回 独立するつもりはなかった】
過去の記事:第1回、第2回
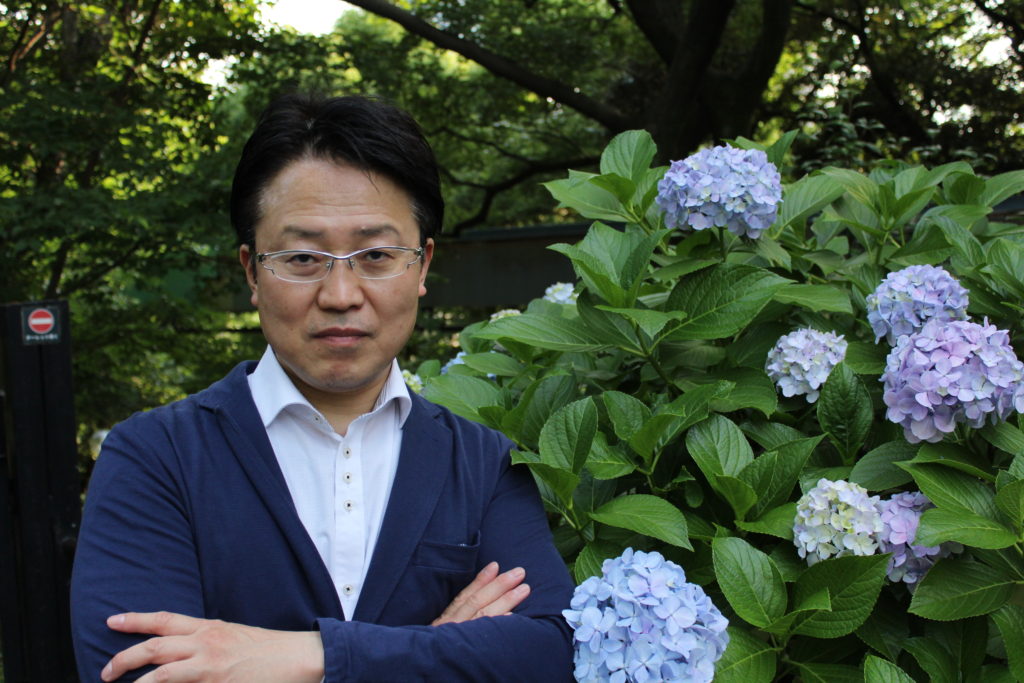
地方銀行に勤めながら中小企業診断士養成課程(以下、養成課程)を経て、登録から1年後に中小企業診断士として独立された菅原寅太郎さん。第3回は、中小企業診断士として独立したきっかけや、養成課程を目指す人へのメッセージをお話しいただきました。
34年勤めた会社の退職を1週間で決断
――独立するつもりで診断士受験や養成課程に進まれたのですか?
定年まで独立することは考えてもいませんでしたね。中小企業診断士に登録してから1年間、ほとんど活動していなくて、何も変わらない状況でせっかく資格を取得したのに、面白くないな。と思っている中で、さらに社内で面白くない人事異動があったんですね。それで、仕事を辞めてしまいました。
――決断するまでどれくらい悩まれましたか?
34年間務めた銀行を、人事異動の内示から1週間でやめる決断をしました。
――1週間の間にどんなことを考えていたのでしょうか。
独立した後に仕事があるのかと、独立する場合と会社員を続ける場合を比較して金銭的にどれくらいの差があるのかを考えましたね。退職金は400万円以上減りましたが、その時の職責は残業代も出ない状態だったので、仕事内容も考えると金銭的には独立しても大きな影響はないと判断しました。
――独立後の仕事のとり方を教えてください。
退職する前から補助金事務局の仕事を少し始めていて、本格的に稼働を増やせば十分稼げるくらいの収入は見込めました。その仕事は養成課程で出会った知り合いからの紹介ですね。その後は、専門家派遣だとか、補助金を申請したりしていました。
養成課程を検討している方へ
――学校を選ぶうえで注意することはありますか?
私が通っていた東洋大学以外にも、様々な養成課程の選択肢があります。学校ごとにかなり個性があって、向き不向きはあると思います。チームで動くことが多いので、人間関係などはやはり気を使う場面もあります。なので、私は事前に調査してから学校を決めましたね。
――養成課程に向いている人、向いていない人はいますか?
養成課程は基本的にチームで動くので、基本的なコミュニケーション能力は必要です。チームを引っ張るとか、統率力がある人とかはもちろんいいと思いますが、自分のこだわりが強すぎる人とか、チームで動くことが苦手な人は、途中で離脱してしまう人もいましたね。
今後の戦略
――独立診断士として今後やっていきたいことを教えてください。
コロナ禍において、銀行がコロナ融資をすごい勢いで行ったんですね。なので、バランスシート上でこれは絶対に返せない、という企業があるはずなんです。そうすると、次に必要になるのはリスケかなと思っています。経営改善計画策定支援事業などですね。
――菅原さんの強みを活かせる領域ですよね。
私自身が銀行で長く働いていた経験があり、銀行の考えていることがよくわかるのでいくらでも交渉できますから、強みを発揮して差別化できる領域だと思います。
それに、前向きな仕事ではないですし、金融機関や銀行との関係性を考えると、あまり多くの中小企業診断士が手を付けたがらない仕事なんですよね。だけど、限りない市場が広がっているということは見えているので、なんとかやっていきたいなと考えています。

木村桃子 取材の匠メンバー、中小企業診断士
1994年生まれ。東京都在住。服飾系大学を卒業後、新卒でアパレル販売職や人材派遣会社を経て、マーケティングコンサル会社に転職し人事部採用担当に従事。合格後は資格予備校講師としても活動中。 趣味は美容。特技は事例Ⅰ(91点)。